|
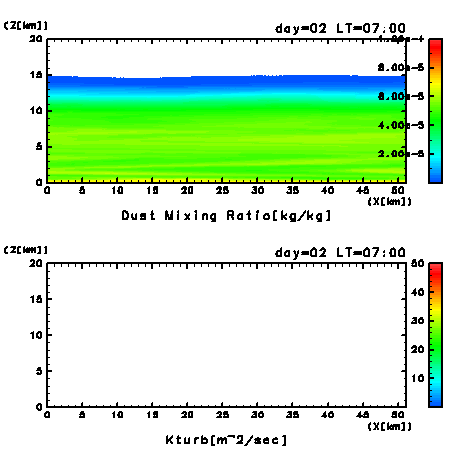
|
|
図 10b : 巻き上げ 2 日目のダスト混合の様子. LT = 07:00 〜 18:00 の
1 時間毎の結果. (上段) ダスト混合比 (kg/kg).
1.0×10-8 以上の領域に配色.
(下段) 乱流拡散係数. 1.0×10-5 以上の領域に配色.
|
高度 10 km 付近にまで達したダストはさらに成層圏内を上昇する.
ダスト巻き上げ 2 日目のダスト混合比の様子を
図 10b (上段) に示す.
高度 10 km 付近のダストは午後になるとプリューム状の形態をとって上昇する.
乱流拡散係数の分布 (図 10b 下段) から,
このプリュームは地表付近に存在するキロメータサイズの対流とは
別の鉛直混合であることが想像される.
この領域の鉛直混合を起こす原因は,
鉛直方向のダスト濃度差にともなう放射加熱の差である.
1 日目のダスト巻き上げと混合の結果,
高度 11 〜 13 km 付近に, ダスト濃度が高さ方向に急速に変化する領域
が形成された (図 11a).
これに伴い, ダストによる日射の吸収は高度 11 〜 13 km 付近以下の対
流層と上層成層圏とでは大きなコントラストが生じることになる
(図 11g,
図 11h 参照).
結果として, 10 km 付近とより上層との間において温位逆転がおこり,
大気は対流不安な状態になる.
水平平均した温位の鉛直分布を調べると, 温位逆転はすみやかに解消されるため,
高度 10 〜 15 km の領域で温位が鉛直にほぼ一様になっていることがわかる
(図 11d (右) 参照).
ダストの成層圏への上昇にはダストの日射吸収加熱が陽に働いており,
この領域においてはダストは受動的なトレーサーではない.
水平平均したダストの鉛直分布はダスト巻き上げ 4 日目以降,
大きな変化は見られない (図 11b を参照).
下層の対流層内では対流層の厚さが薄くなるのに伴いダスト濃度は若干増大している.
上層ではダストが平均的にゆっくりと沈降するのにともない
ダスト濃度は若干減少している.
|